今だから通じる『Z(ゼータ)』の意味。
誠実であろう人ほど孤独になりやすい世界の構造。
たとえば──
- 本音よりも「空気を読む」ことが優先される学校職場という社会文化
- 冷笑や炎上をしながら、大人を名乗りながら敵を求めている空気感
- 「正しさ」という言葉を用いて、逆に人を強制し、縛ってしまう風潮
これらに基づいた生きづらさは、時代の構造的副作用とも呼べる。
つまり「個」としてではない物が求められ、誠実であろうとする人が孤立する時代に生まれたが故に生じている。
また「承認欲求がマネタイズされ、貨幣になる」構造は現代において段階的に進化してきた。
概念自体は1970年代のマスメディア的な注意経済にまで遡れる。
が、実際に「承認=収益」が人々の精神に大きく影響を与えるレベルで顕在化したのはスマホ+SNS普及後、特に2010年代以降。
つまりここから“承認を得る現代において作る”から“懐を潤す/自己を整える(正義)のために書く/作る”へ目的を転換するようになりつつある。
デジタルネイティブに生き、情報過多や経済的不安、社会正義志向、精神衛生への敏感さを抱え、既存制度に対する懐疑と自己表現の両立を迫られており、制度や既成概念に疲弊しつつも、共感を求める時代を生きる人間を、我々は「Z世代」と呼称している。
そして因果なことだが「Z(ゼータ)」という記号が持つ終末性・転換性と、現代の“Z世代”の抱える特徴を重ねると「人間社会の行き着く先」めいた暗喩を意図的に描かれたのがあの有名な『Zガンダム』である。

ニュータイプという新しい感覚装置を知りつつも、同時に不安定な現実を抱え、自らの感情を抑えきれず、それでも人を理解しようともがいた結果。『Z』の主人公であるカミーユが見たのは、理想と現実の激突による自己の崩壊。

クワトロ (シャア) の語っている人の理想と誠実さを信じ、世界を変えようとする。シャアが持つその理想に共鳴し、カミーユは心中を晒しながら懸命に敵味方に語り続け、戦い続けたが、相通じずに理解されない世界の中で精神を摩耗していった。

そしてそれは、単純な「終末」の提示ではなく、この師弟の二人が描こうとした「理想が腐敗し、理性だけでは回復できない社会の病理」を抉るための物語的実験でもあった。
これは作品の主題とも現代の世代像とも不思議なほど呼応しており、『Zガンダム』が初代の「理想的ラスト」を解体して見せたように、今日の若い世代もまた既成の価値や制度の終焉を前に生きているのは、おそらく一種の必然ではないかと筆者は感じている。
理性の崩壊から、感情の復権へ
――『Zガンダム』における「勘と怒りの正当性」から読み解く富野由悠季の再出発の集約された回は、『ZZガンダム』終盤のあるシーンで描かれた。
「私には戦わねばならぬ大儀がある。お前こそ正義など見えないのに何故戦う? お前はただの兵士だから戦っているのだ。
お前がガンダムに乗っているのは状況にすぎん。しかし私は違う。自ら過酷な生き方を選び、後悔はしていない。お前には内から沸き上がる衝動はあるまい!そんな屑は、私の前から去れ!!」
「違うよ! 俺には個々の人の…欲望が起こす間違いだけは分かるんだよ!
だから…俺は…」
『その君の勘から発した、君の怒りと苛立ちは理由になる…!』
グレミー・トト
ジュドー・アーシタ
カミーユ・ビダン
この言葉を初めて聞いたとき、ある人は戸惑うだろう。
「怒りや苛立ちが“理由”になるのか?」
世界では、怒りはしばしば“未熟さ”や“病”として扱われる。
しかしカミーユは、理屈で言葉を選ぶよりも、その先に感じ取った痛みこそが、真実に至る手がかりになると信じていた。
この発想こそ、富野由悠季が『Zガンダム』と初代の理想を超えて描こうとした人間の姿である。
初代『ガンダム』――「理性による希望」という完成形
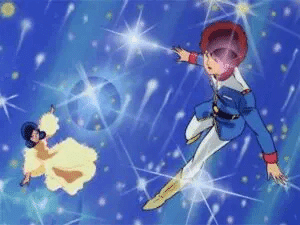
『機動戦士ガンダム』(1979)は、アムロという進化を象徴する若者が「他者との和解の可能性」という形で物語の果てに到達する物語だった。
人類がニュータイプという新しい感受性を得ることで、分かり合える未来がある――そこには、数々の別れや悲惨な現実が待っていた戦争の悲劇を超えて“希望”を描こうとする強い理想があった。

しかし、この理想の結末を富野は「キレイすぎる」と感じる部分も多少はあったのだろう。
惹かれ合いながら死別したアムロもララァも、最後には「理解し合えなかった痛み」よりも「理解できるはずだった理想」を尊いものだと語って見せた。
確かにそれは文学的には美しいが、人間の現実とは乖離していた。
初代『機動戦士ガンダム』は“ニュータイプによる理解と和解”という希望的結末を提示したが、富野はそれが「現実との乖離」を生んだと同時に自覚していた。
『Z』はその同じ世界を「理想が腐り、制度が人間を抑圧する」局面へと押し広げ、初代の“綺麗さ”を自己批判的に解体する作品になっています。
富野監督は人の理想を描いたはずが、いつの間にかその理想に「置き去りにされた」ことを見逃せなくなったのも初期衝動として大きいだろう。
『Zガンダム』――理想が崩壊した後に残る「怒り」
『Zガンダム』(1985)は、そんな初代の理性を否定する物語として始まる。
新主人公であるカミーユ・ビダンは、理屈よりも感情で動く少年だ。
身勝手な両親や理不尽な大人、腐敗した軍人たち、偽善的な組織、嘘の正義――彼の怒りは、社会の表面を覆う欺瞞を撃ち抜くための本能的反応だった。
そして、彼は後にこう言う。
「君の勘から発する怒りと苛立ちは理由となる」
それは、世界そのものが理屈が通じないように築かれたとき、人間の“勘”だけが最後の真実を掴むという信念だ。
この「勘」とは、知性ではなく、誠実な感受性のことだ。
他人の痛みに共鳴する力、違和感を無視しない感性、目の前の不道理に怒ること。それらは論理や説明を越えた「人間の信号」だ。
富野は、理屈を超えた感情の中にこそ、人が人である根拠を見出そうとした。『Zガンダム』は「理性による繋がりの神話」から「感情の倫理」への転換点だった。
つまり人間社会がここまで来るとこうなるという警告的暗喩を含みつつ、「ここからどう立て直すか」を問う作品として掲げられたのだ。
そして続編『ZZ』で新たな主人公のジュドー・アーシタが登場する。
彼は同じく誠実だが、カミーユとも違って「人間を明るく見放さない力」を持っていた。彼の強さは、絶望を知ってもなお笑い、生きるという抵抗だ。
理想の崩壊と、富野の自己批判
カミーユの物語は、結末で狂気に至る。
だが、それは“狂ったが故に精神を壊した”というより“理性の限界を越えた”という描写が続いてきた故のものだ。
理屈では世界を救えない。しかし、世の中を見通して感じてきた怒りもまた世界を滅ぼす。
富野はその矛盾を避けず、正面から描いた。
彼は、初代で理性を信じた自分自身を、Zで批判していたのだ。
この思想的流れは、富野自身の人生とも重なる。
彼は初代ガンダムを通して“理性ある大人”を描こうとしたが、現実の社会はその理想を裏切ったのもあるだろう。
無論、続編を求める人々の声もあったが、スポンサー企業やメディア、どこか「綺麗すぎる物語」の神格化による押し付けた教育――どれもが“理屈”を使って我が物顔で振る舞おうとし、感情を押し殺す形を示してきた。
これは、本記事の序盤で見せたように70年代の流れでもある。
だからこそ、彼はZで「怒り」と「苛立ち」に正当性を与えた。
それは、狂気ではなく誠実さの証だった。
『ZZ』『逆シャア』への橋渡し――怒りと寂しさの先に「強いの子」を見つける

カミーユが壊れた後、ジュドー・アーシタが現れる。
彼は怒りを乗り越え、「人間として生きること」を取り戻す存在だ。
Zで燃え尽きた怒りの先に、再び世界と繋がろうとする姿。
それは富野がZで描けなかった「希望の再定義」だった。
「………分かったよ。俺は間違いなく、身勝手な人の独善に対して、みんなの意志を背負って戦ってる!」
「みんなの意志だと?」
「お前は血のことを言ってるようだけど、その原点は何処から来た?
地球だろ。全てのものを生み育んできた地球が、俺達の故郷だ。
ザビ家の血なんてその中の何千億分の一だろ!
そんなことが原因で争うならアクシズの中だけでやってくれ!
地球は汚染されてるし、俺達のコロニーは古くて腐ってる。
今は、人類全体がやり直さなくちゃいけないんだ!
あんたみたいな小さなことにこだわる人間は倒さなくちゃ明日は見えないんだよ!血に縛られたような連中は、邪魔なんだよ!」
「…ジュドー!」「お兄ちゃんなの…?」.
「人間の可能性を、ちっぽけな自己満足の為に潰されてたまるか!」
『ZZ』終盤でジュドーがグレミーに叫ぶ場面は、カミーユの在り方から背中を押されたこともあり、どちらも、理屈ではなく感応によって世界と接することを肯定するものだ。
ただ『ZZ』ではそれが怒りではなく「他者への共鳴」へと昇華されている。
富野が初代から再び歩き出した道の果てに“怒りを越えた理解”があった。
人間であり続けるために「君の勘から発する怒りと苛立ちは理由となる」――この言葉は「君が感じた本能的に感じた不快感には意味がある」という、時代を超えて通じる哲学だ。
集団の中で、理屈や正義を武器に殴り合う社会、冷笑と炎上、怒りや悲しみが個々の欲望やマネタイズとして徴収され、嘲笑される世界の空気。
そんな中で、違和感や痛みを感じ取れる人はまだ「人間」だ。
「それじゃ、死んでいった連中はどうなる!ええ!?ブライトさん!いっぱい死んだんだよ、いっぱい!」
「分かっている。気に入らないなら、俺を殴って気を済ませろ」
富野は“理性を捨ててでも人間であれ”と言ったのではない。
“理性を越えてもなお、誠実であれ”と訴えた。
それが、カミーユの怒りであり、ジュドーの優しさであり『逆襲のシャア』で見せた光のような、富野由悠季が長年かけて描き続けた“人間賛歌”の核心である。

カミーユやハマーンがNTでありつつも「分かり合えないこと」に絶望したのに対して、
後を継いだジュドーは「それでも分かろうとしながら強くある姿勢」を貫いた。
「勝ち負け」や「正しさ」ではなく、
“人と人が響き合う瞬間”=バイブレーションに希望を託していた。
- Z世代:理性と誠実が崩壊する時代。
- ZZ世代:感情と他者理解の再構築が始まる時代。
この「バイブレーション」という言葉が重要なのは、
“論理”や“思想”ではなく、
感情や生理的な共鳴こそが人間の根本的理解の形であると示している点。
ジュドーは理屈ではなく“感応”の側に立つ。
論理・建前・効率・承認の地獄のような世界の構造のなかで――現代の我々が抱える“心の構造”にも似ている。
誠実に物を見ようとすれば、必ず矛盾や偽善に突き当たる。
しかし、それでも対話を放棄しない勇気が、人間を“狂気ではなく人間”として繋ぐ。カミーユの「叫び」を、ジュドーは「共鳴の震え」に変えた。
それが“バイブレーション”という言葉に象徴されている。

それは、まさにZの時代が続いてしまっている状況からのカミーユ・ビダンの精神崩壊を乗り越えてなお、
そのZ世代(理性で分かり合えない時代)を超えたいという“人間として生き抜こうとする意志”が脈打っている。
Zが描くのは「理想の終焉」だが、その末路から再定義へ動く力も提示される。Z世代もまた“古い価値の終わり”を見据えつつ、別の生き方やコミュニティの在り方を模索している点で似ている。
人間は理屈だけでは生きられない。
本気で誰かを思い、怒り、悲しむとき、そこに理屈などない。
それでもその感情の波動が、他者の中に震えを伝える。
その震えこそ、人間が人間である最後の証だ。
まだ希望はある。
それは同調や決められた正解を超えて「自分の声で世界を感じる」という行為のことだからだ。
生きることは、しばしば「存在の孤独感」を伴う。
それを自覚して尚、愛を通じて他者を信じ、繋がりあおうとする意識が感じ取れないと、本当のバイブレーションは感じられないものだ。
それを感じ取れる者こそが、“人間の強さ”であると呼べるのだと思う。

星が降りしきるペントハウスで
空のオルゴールひとり聴いてた
ガラスのロープを目隠しで渡る
みんな淋しいサーカスの子供さ
ひとりぼっちの哀しみに
軋(きし)んだ綱が 心で揺れてる…
Silent Voice, Silent Voice
優しい瞳(め)をした誰かに逢いたい
Silent Eyes, Silent Eyes
ささやいてくれよそばにいるよって…
サイレント・ヴォイス
