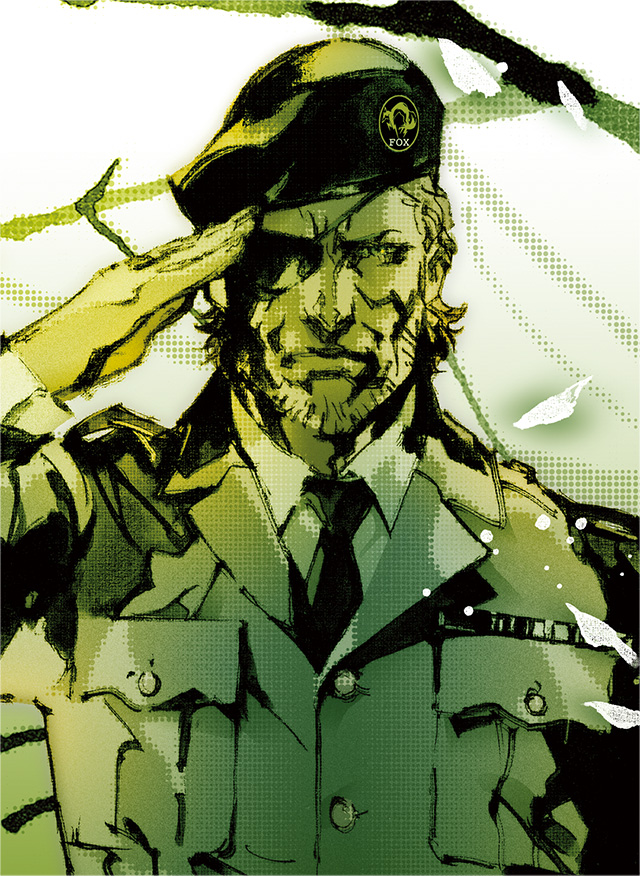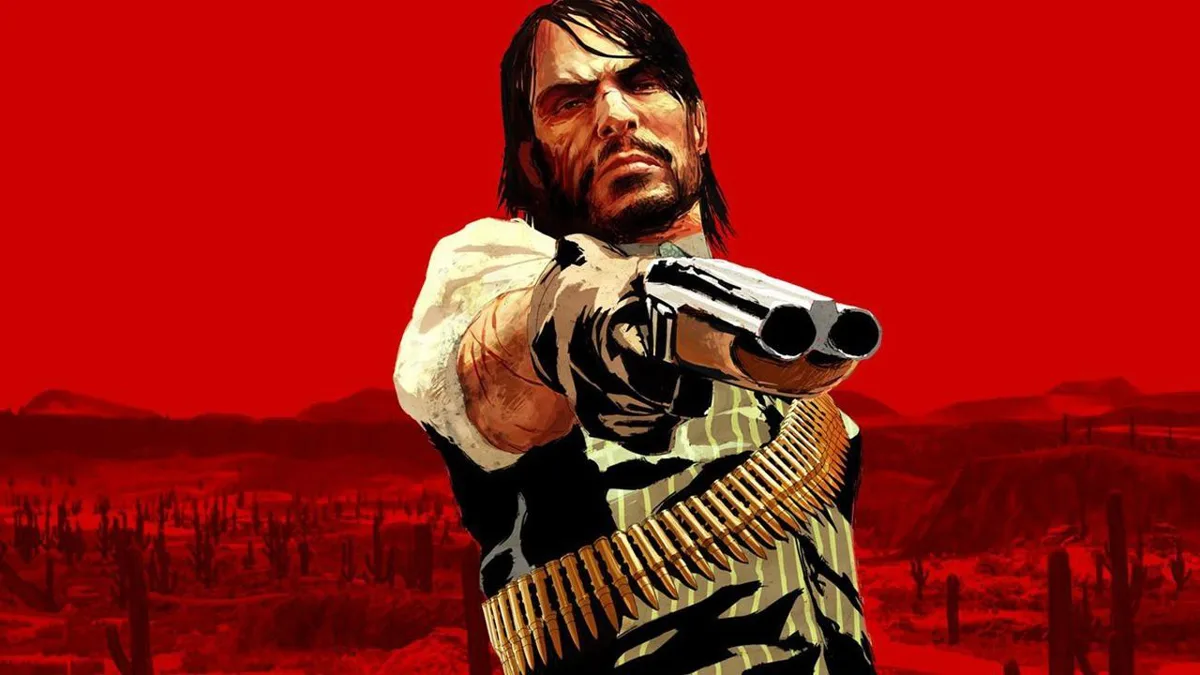新着情報
KISERU GARDEN
Twitchチャンネル
元演劇畑の読書家ライターという美の探究者による、
文章を中心とした色々なエンタメ作品を解説やら考察して物語るためのブログサイト。
また、人生というゲームをどう生き抜くのか無理ゲーというレビューが満ちるこの世の中について一緒に考えましょう。
現在、新たな価値創出や人々の生き甲斐を創る第一歩として、音楽やインディーゲーム制作等にも携わっております。
このサイトやSNSを接点として、お見知り置き頂けたら嬉しいです。
これからYoutubeやTwitchでの活動も予定しております。
もしよろしければチャンネル登録頂けると嬉しいです。