復讐の影から、希望の灯火へ
「I’m vengeance(俺は復讐だ)」
『THE BATMAN-ザ・バットマン-』より
その台詞から始まる『The Batman』(マット・リーヴス監督)は、これまでのバットマン像とは一線を画す作品だ。だが、単なるリブートではない。
本作が私の心を捉えて離さないのは、現代における「正義」の輪郭を問い直しながら、その問いに誠実に向き合おうとする一人の人間としての、ブルース・ウェインの物語だからだ。
彼はヒーローではなかった。
少なくとも、最初からそうであったわけではない。
復讐の仮面と、共鳴する影

本作のブルースは、まだ若く未熟で、何より怒りに囚われている。両親を殺され、法が無力であることを悟った彼は、自らを「復讐」と名乗り、バッドマンという仮面の中で正義を遂行しようとする。
だが、そうした「私刑による秩序」は、同じく怒りを抱くもう一人の仮面の男、リドラーによって踏み越えられていく。
リドラーはバッドマンに向かって語る。
「自分たちは同じだ」と。
腐敗したゴッサムに見捨てられた者たち、ブルースは両親を失った孤児として、リドラーは希望を語るリニューアル計画に裏切られた孤児として。
彼らは同じ地平から出発している。だが、リドラーは暴露と処刑を手段とし、ブルースはやがて「象徴」として市民に寄り添う選択をする。
この倫理的な分岐点こそが、『The Batman』が語る最も現代的なテーマである。
情報と暴力の時代における“正義”の再定義

リドラーの制裁は、SNSを通じて拡散され、模倣犯を生む。
匿名で暴力を行使する集団は「真実を暴く」という大義名分のもとに他者を傷つける。
これは、現代のネット空間で頻発する「暴露系」「正義中毒」と何ら変わらない。
情報が力を持ち、告発が快楽化し、「正しさ」が暴力にすり替わる構造。
本作は現代の群衆心理と正義の危うさを映し出している。
「信じれば残酷になり、否定すれば凶暴になるもの、なーんだ?」
「答えは正義だ」
映画『THE BATMAN-ザ・バットマン-』特別予告(世界の嘘編)2022年3月11日(金)公開

ブルース・ウェインもまた、当初は「暴力による秩序」を選んでいた。
だからこそリドラーと重なり得た。だが、彼はその“誤解された正義”の行き着く先を見て、ようやく気づく。
象徴とは恐怖ではなく、希望であるべきなのだ、と。
父の遺産と自己の倫理について
もう一つ、本作が深く切り込むのは「遺産」の問題だ。
ブルースが信じてきた父のトーマス・ウェインは、表向きには理想主義で、ゴッサム・シティを救おうとする存在だった。
しかしリドラーの告発によって明かされるのは、彼もまた暴力と妥協の中で「善」の定義を曖昧にしていたという事実。
ヒーロー神話の裏にあったのは、人間としての過ち。
それを知ったとき、ブルースは絶望するものの、それでも彼は父を「善き人間として葬る」のではなく「過ちを認め、引き継ぐ存在」として自分を再定義することを選んだ。
それは、私たちが今この時代に「誰かから継いだ価値観」や「正義」について考え直すときに必要な視座でもある。
善と悪は単純に分けられない。
むしろ、その狭間で人は、倫理的にどこに立ち続けるかを常に試されているからだ。
『ダークナイト』の象徴的な「選択」のシーン
『ダークナイト』 (2008年 クリストファー・ノーラン監督作)において「フェリーの二隻が互いに爆破スイッチを握る」シーンがあります。
アレは本作の倫理的・哲学的テーマを象徴しており、
フェリーの一隻には「民間人」
もう一隻には「囚人たち」が乗っている。
そうしてどちらかが先に相手の船を爆破すれば自分たちは助かるが、午前0時になれば両方爆破される。
爆破スイッチを手にした人々は、「正義」や「自己防衛」の名のもとに、他者を犠牲にするか否かを迫られる。
これは明らかに、敵であるジョーカーによる“道徳実験”であり「人間は状況次第で容易にモンスターになる」とする彼の信念を裏付けるための罠でした。
「人間はほんの少しの恐怖と混沌で“倫理”を簡単に捨てる」。
だが、誰も他人を爆破しなかった。
これは、ジョーカーの“人間不信”や“秩序への憎悪”に対して「人間性」そのものが最後の瞬間に超えたことを意味しています。
民間人が囚人を爆破しようとすることは「正義」とすら見なされかねない。
だが、実際には名もなき囚人側の一人がスイッチを黙って放棄する。
この行為は強い倫理的主張を持っています。
彼は「人間性の最も低い場所にいると見なされていた囚人」でありながら、最も高い道徳的判断を示した。
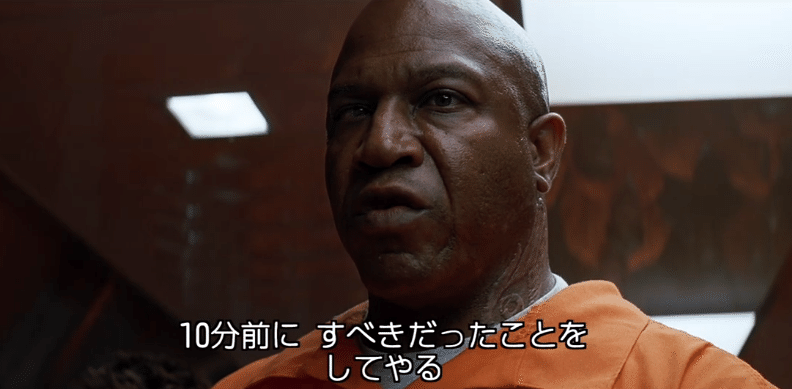
スイッチを囚人が手に取った際に「彼が押すのだろう」と思ってしまった等、これは我々自身にも突き付けられている。見かけや身分ではなく“選択”こそが倫理を生むというカウンターがここにあります。
「人間は信じるに足る存在である」という前提で行動してきたそれに対して、ジョーカーは「混沌と恐怖で人は簡単に壊れる」と主張した。
このフェリーのシーンにおいて、最終的に選択を下したのは市民たち自身でした。単なる「善人と悪人の構図」ではなく、二項対立に飲み込まれることへの拒絶を描いています。
民間人 vs 囚人。正常 vs 異常。善意 vs 悪意。
このような二項対立に私たちは現代でも頻繁にさらされています。
ネット上では「敵か味方か」の構図が即座に生まれ、それを参照するかのようなイイネという同調圧力や空気が生まれ、互いに“爆破スイッチ”を押したがるような空気が蔓延している。
それでも、人は「押さない」という選択ができる。
『ダークナイト』もまた暴力や報復の衝動を抑える「理性と倫理の力」を信じた作品です。
他者との関係性の中で生まれる選択

セリーナ・カイル(キャットウーマン)の存在も、ブルースの成長に大きく寄与している。彼女もまた傷を抱えた復讐者でありながら、「逃げること」もまた倫理的選択であると示す。
他者に依存せず、過去に囚われず、自らの手で未来を切り開こうとする姿は、ブルースにとってもう一つの「あり得たかもしれない自分」だ。
そして彼は選ぶ。
灯火であり続けることを。
瓦礫の中で市民を抱きかかえる彼の姿は、もはや恐怖を撒き散らす黒い影ではない。
人々が彼に手を伸ばすのは、怒りではなく信頼の証だ。
私が『The Batman』に惹かれた理由
私が本作に深く惹かれたのは、それが単なるヒーロー譚ではなく、倫理の迷いと自分自身の再構築を描く物語だったからだ。
正義とは何か。
怒りをどう扱うか。
他者の遺産はどのように受け継がれるべきか。
傷ついた者と、どう関係を築けるか。
現代という「正しさ」が簡単に暴走する時代において、ブルース・ウェインの選択は誠実な生き方だと感じる。
完全な人間ではなく、迷い、傷つき、それでも希望を灯そうとする姿に、私は道を照らしてくれたような気さえする。
復讐の影から、希望の灯火へ。
『The Batman』は、その変化を静かに、しかし力強く描いていた。
だからこそ私は、この作品に何度でも心を打たれるのだ。
