ネットの結びつきの本懐は「FF(フォロバ)」にある
ヒト・モノ・コトを司るネット社会では、金銭的な商取引や身分証明書の提示を他者に求めることもできるし、そのような現実の責任に基づいたビジネス関係を作れるようになった。しかし、ネットにおける一般的なコミュニケーションの大部分は、現実を担保とするような言論責任も余程の悪意や過激さが伴わなければ求められない。
これは時代が進むと現実の延長線にSNSを用いられている空気が蔓延していながらも、そこで紡がれた繋がりに伴う責任や自分たちの関係性を口にするほど必要としていないのは、現代社会において着目すべき点のように思える。
従来のコミュニケーションとしての「匿名性」を維持しながらも、人間関係の最適化としてソーシャルに示されたいわゆる「フォロバ(FF)」など上下関係といった「主と従」とは別枠として言語化され、ネット上の人間関係のデフォルトとして受け入れられているからだ。
今日で呼ばれる「活動者」とは何者なのか?
このフォロバ精神もといウィンウィン現象は発信者/配信者の活動を、古典的な芸能ビジネスと捉えている人たちは既に名が知られている芸人・声優・アーティストやアイドルがYouTuber/VTuberになってもいわゆる「推し」とする熱量が見られないことに直結していると思える。
彼らのチャンネル登録はするし、配信や動画を見るという行動は実のところ「推している」とは別の「一方向性的な従来のテレビ番組」として扱っているという心理的差異があり、自らをコミュニティに帰属させて等号(イコール)で結びつけられる「ご友人」には成り得ないからだと推察できる。
双方向的な関わりの上で成り立った現代の「動画投稿・配信文化」
新しい自己表現、新しい関係性のためのツールとしてネットが利用されるようになった結果、いわゆる案件として動画投稿者やYouTuberライバーなど配信者に企業が商品PRを依頼するのは、彼らに対するファンの親密度が高いから、扱われた商品を自分も試したくなる訴求力が強いからだ。
かつての広告業はなるべく人の目に止まってもらってゼロから商品に関心を持ってもらうこと。これがいわゆる消費行動を促す手段として紙面の広告に限らずCMやバラエティなどTV番組の合間にスポンサーとして紹介されてきた。
それ以外でも流行歌や恋愛やファッションもまた一世を風靡したと言われるドラマや俳優のブランドやシチュエーションなどで消費活動を促す。
いわゆる「夏祭りやクリスマスは特別なイベントデーで恋人と過ごす」というのも長らく日本独自の文化として醸成された一方向的な発信メッセージが人々に浸透した結果であり、バブル期などで築かれた消費行動を促すために理想像を示されたものだと言える。
現代のメディアは当時の成功体験を引き摺っているままで、技術発達した現代の「双方向性的な社会」を従来の手法のフォーマットに当てはめてビジネス化を試みているが、この社会的同調圧力がすでに不適切であるとして考えられている。
何故なら、景気の好調などで支えられた消費行動の時代背景には、ステータスの誇示や社会的地位の追求を人生設計の目標とさせる「充実した人生のモデルケース」を掲げている方へ志向していたからだ。
キッカケは「自分のことを誰も知らない世界」への憧憬
この潮流に抗ったのが、いわゆる現実の自分のことを「誰も知らない土地」での再出発。
そこで思うように生きられるのでは、と従来の自分とは切り離した匿名性のある関係同士でコミュニケーションできる居場所だ。
現実の関係から切り離された「別のスタートラインでやり直したい、理解されたい」という強い動機から、現代までに至るネット社会におけるユーザー名、ハンドル名、異なる名前を冠する性質というものは、これに基づく動機がある。
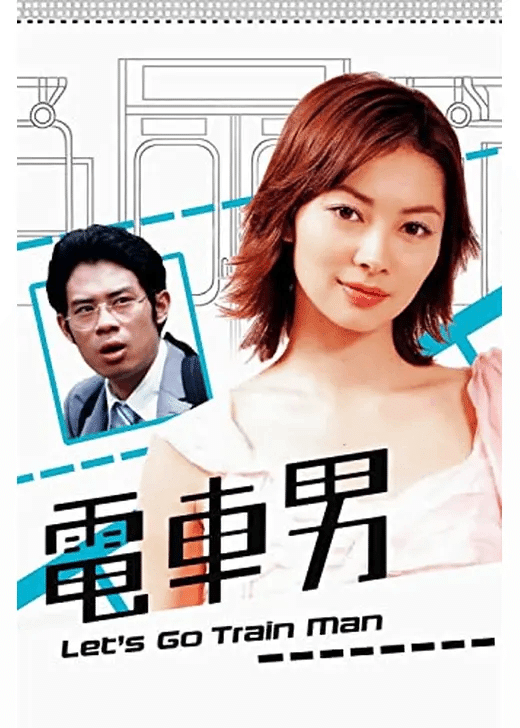
深淵の中で暗く醸成させてきた感情はネットに限った現象ではないが、人は状況に応じて、そのロールに応じて価値や承認を得ようとする。
一緒くたに言ってしまえばライトノベルや異世界転生的なジャンルの訴求力もこれにあたる。その共通項である欲求から相互的に人を結びつけてきたのが「ネット」であり、たとえ身体性を見せなくても、自分の趣味趣向、愛用しているもの、愛しているモノを語って紹介してみせることも、その実在性を深められ、本人との繋がりや理解を深める契機になる。
この過程で「なりたい自分」「なれるかもしれない自分」を演ずることを選ぶ人もいるだろう。「バーチャル空間の存在」として現代で掲げられている「メタバース」「Vtuber」然り、それらの先駆けとも呼べるMMORPGもその一環だ。
ネット社会は「暗黙の了解」の相互信頼から成り立つ隣人愛
なので、最近メディアに進出している存在としていわゆる「VTuberは触れ合えないだろ」というのは実は危うい感覚だ。
何故ならキャラクターの実体を伴っている「人間性」を否応なしに捉えようとする視聴者の本能に働きかけてみると、彼らが人生で体験してきたこれまでを紐づけたキャラクターが自己実現の形として成り立った存在ならば、遠巻きで崇め奉る非日常的な「アイドル(偶像)」ではなく『対等な存在』として見てしまうからだ。
最初期に掲げられたようなキャラクターや設定ロールに徹したVTuberよりも、中途半端に現実をチラつかせて自らの日常や生存を仄めかしながら「苦闘の日々を生きる同志」としての「同胞愛」やら「友情」「信頼」を基盤にした人間的な情愛に訴えかける故に、キャラクターであるはずが「個人」として代替不可能な方向に突き進んだのが今日のVtuberだ。
よって多くのバーチャル活動者は原理的にそのような恣意的な工夫から人気を得ているという暗黙の了解の上でキャラの役名は自動的に、演者として扱われている個人を自ずと指し示すものとなる。
故に「友達感覚」やら「ネタとして見ている」という風に追っかけとしてのモチベーションや動機を詐称し、自分自身でファンを自認することもない「無自覚な推し活」として成り立ち、客層としてもっとも理想的なモデルに位置することになってしまう。
だからこそ、ネット上で自分自身を消費者サイドに位置すること、つまり「客」や「ファン」と自認するケースを見かけなくなってきた現象としてなぜか次第に置き換えられた言葉である「リスナー」や「推し」は流行りのスラングという捉え方もある。が、おそらくそれ以上にこの意味合いは、無自覚な「隣人愛」という性質を帯びつつあると呼べるのだろう。
「親愛なる隣人」を御旗としたコミュニティ形成
ネットの発達と共に文字の発信から「音や映像」といった表現手段を獲得し、バーチャルリアリティの先駆けとも呼べる匿名性と自己表現のニーズに適応したブラウザやアプリツールが広まったのが、ネット社会の共同体形成、無頼の遊牧民からの「コミュニティ(集住時代)」だ。
ネット活動者の性質をコンテンツとするのであれば、始まりは対等な関係、あるいは同じ価値観を共感した仲間になれるかどうかで評価している。
そうして視聴者はコメントや反応を通じてフィードバックを提供し、新しいパーソナリティを共創している視聴者との相互作用は、ネットの中の活動者を「他者」として受け入れるか否かが肝要だ。
そのために自分と同じクラスターの人間であるとホールドアップして見せること、実は相容れないこともあるかもしれない摩擦や社会的属性、それらを互いにスルーし合うことで、自分の関心のあるモノやコトについて「同じ主義思想として体現したり、共鳴し合える仲間」
つまり、匿名性を帯びているその人となりを言葉にする際は「記号的・情報的価値の大きさ」からその人を評価することになる。
キャラクターとして分かりやすい例として言い換えてみるなら『コードギアス』というアニメ作品では皇室に棄てられた巨大帝国の元皇子として自分の一族に対する復讐を決意し「圧政者である帝国に抗う仮面の男『ゼロ』」という素性不明の仮面(ペルソナ)を被る主人公の下に、彼の正体を問わないまま「日本を解放する正義の味方」として共鳴した日本人レジスタンスが集った関係性がそれに近い。
ある意味では、そういった分かりやすい属性を付与、何か役割を取り決めて人を束ねる仮面(ペルソナ)が「○○系」のYouTuberやインフルエンサーであり、その人が何者かを規定するにはネット上ではその人自身の思惑や真偽ではなく「所属コミュニティとの関わり方や情報的価値として有用か否か」
あるいは自分たちに害をなすことなく、むしろ豊かにしてくれる相手なのかを問われるという、実は従来のネット社会における「匿名による対人心理の延長線」に敷かれている支持なのだ。
「推し活」とは「同郷の隣人」を守り育て上げること
故に「一般人のバズり」が一過性のものとしてチャンネル登録者は増えてもリスナーが増えないのも、匿名性を帯びた発言者が何者であるかが明言されないとエンゲージメントは生まれにくいからだ。
バズったものが何かしらのジャンルに属するならまだしも、昨今のネット大喜利の類であればなおさら発言者自身に目が行きにくい。
ネットを埋める分散的なコミュニケーションは誰もがネットの荒野や大海原を彷徨う遊牧民だった時代から、集合住宅的な住まいを求めて土地が開拓され、そこで起きたコミュニティが権威性を帯びるようになった。
いわゆるコミュニティを形成する旗印となる「活動者」と呼ばれる人たちは「従来のネット社会の人間関係」の上に成り立つ存在であって、旧来の芸能人やアイドル的な人気の上で成り立つ存在とは言い切れない。
完全なる他人と言い切れない「同郷の身内」に近い距離感だからこそファンは「杞憂」と言われるように活動者を「自分事」として気にかける。
「推し活」というクリエイティブを育て上げるコミュニティに帰属意識を持つだけで自尊心も保てる。「応援」というのも対人関係の一環として対象者ありきで、根源的には自分の人生の充足のために行われる。
その対象の誰かによって自分が満たされて心地よく、満足できる状態であろうとする利己的な一面を完全に切り離すことはできない。
「活動報告」を重ねるたびに周囲の歓心を買い、コミュニティに対する貢献や称賛が生き甲斐として重要なウェイトを占めているということだ。
こうした意見に対し、真面目に活動しているという人に限らず、アイドルや芸能人的な地位を目指しているネット出身の活動者の中には拒否感を抱くこともあるかもしれない。
が、あくまで隣人として見られている状況下において、長期的なロールの遂行やキャラクター維持の期待を背負って見せるペルソナの必要性というのは界隈を見回す限り否定できないだろう。
蜜月な関係故の「コミュニティの閉塞と衝突」という課題
対面的な人間関係の煩わしさを抜きにして、人とのコミュニケーションを楽しめる「新しい人間関係」がネットでは生まれているということは、当然ながら憶測や根拠なき偏見を持ってしまいがちなネガティブな側面もある。
加えて、自分にとって有意義が繋がりが構築されていないと感じた場合、当然その価値は低下して、コミュニティ内での言動や責任感や期待というものも持ちにくくなる。
人間が集った共同体の本質とは人格を持ち、好き嫌いの仕分けからはじまって愛憎やら敵か味方の区別、駆け引きの中の押し引きを繰り広げ、所属コミュニティ内の出来事の愚痴や悪口を言っていることが、日々の営みの渦中に置かれてしまう。
それがネット空間上であるならば、さらには四六時中繋がってるような錯覚に夢中になるから、冷める時間が設けにくい。
特に我々は自分にとって気に入らない発言を断罪しながらも、周囲のご機嫌取りに甘んじるなどネット上でも日本的文化が残存しており、こういったいじめやハラスメントの構造を理屈として知っている。
しかし、そのはずが自分事は黙認して「敵」を裁きたがって「味方」の共感や歓心を買うパフォーマンスなど敵意を煽った分断や、安直な感情に振り回されるような言論のファストフード化が進んでいる。
特にコミュニティが拡大して発信者の所属先がいわゆる大手になればなるほど、選民思想的な排外主義が加速しているのが目立ってきている問題もあるかもしれない。
僕はいわゆる「推し活」という、その言葉を安易に振りかざして経済活動的な面を含めて無邪気に肯定されること自体には危惧している。
それは酒やタバコといった依存性のある刺激物を未成年に禁止する一方で、ネット上で摂取できる刺激物との関わり方についてオトナ側も教えられないで夢中になっているという現実があるからだ。
自己制御する術を知らないまま、常軌を逸するヘイトやフェイクニュース、精神ポルノばかりが蔓延している動画サイトやSNSの言論空間は日常や現実を侵食する形でここ数年顕在化し続けている。
ネット上のコミュニティや繋がりを起源とした話をトレンドとして現実に持ち帰ってしまったり、そのクソデカ主語トークによる権威性を笠に着た過激な言動や思想、物事の印象操作といった作話やコミュニティ間の衝突は恒常的に発生している。
執筆の容量が増えてきたので今回は「推し活」というモノの捉え方とそこから生じている問題点について挙げてここで締めくくることにするが、なにはともあれ本記事を読んで「身内ノリを他所に持ち出すな」というネット界隈の古来から伝わる教えはどうなってんだ教えはって口にできる大人がマイノリティと化していることに気付いた方は、改めて注意喚起してほしい
